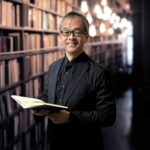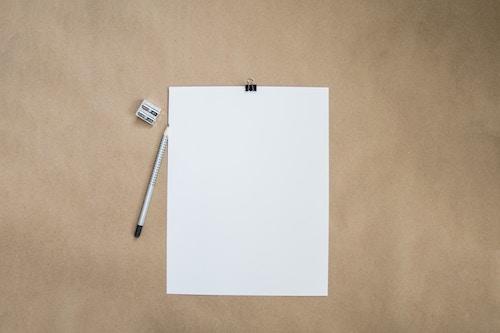研究者を目指すなら、大学院生は複数の研究テーマをもつべし【実例付】


本記事では、「大学院生が生き残るにはどうしたらよいの?」という疑問に応えています
- どんな研究テーマがヒットするかわからない
- 大学院生は大学院で取り組む研究テーマの他に、時流にのった売れる研究テーマの2本柱で研究しよう!
- 時流にのった売れる研究テーマはJREC-INなどをチェックしていると見つけられることも
大学院生は複数の研究テーマをもちましょう
結論から言うと、大学院生は大学院で取り組む研究テーマ以外に、時流にのった売れそうな研究テーマでも研究した方がいいです。
大学院は修士課程(博士前期課程)が2年、博士後期課程が3年というように限られた期間内で成果を出す必要があります。
なので、大学院で取り組む研究テーマは、おのずとそうした現実的制約に基づいたものになります。
すると、挑戦的な研究には取り組みにくくなります。
また、大学院で取り組むたった1つの研究テーマが当たるか否かもわかりません。
もしかしたら、学位はとれても社会的にまったくインパクトを与えないこともあります。
そうしたリスクを勘案すると、大学院生は複数の研究テーマを持った方がいいという結論にたどりつきます。
ぼくも大学院生時代、複数の研究テーマに取り組んできました
ぼく自身は大学院生として非構成的評価の研究に取り組みました。
非構成的評価とは自然な観察と会話で行うものです。
なので、その結果に対してどうしても「あなたがそう思っただけでしょ?」という批判がつきまといます。
ぼくは大学院時代に、結果の確かさらしさを基礎づける条件と教育プログラムを開発しました。
その成果は研究論文や博士論文の他に、書籍としてもまとめています。
これとは別に、独立に信念対立解明アプローチの体系化に挑みました。
信念対立解明アプローチは医療保健福祉領域で生じる信念対立を解消するために開発した哲学的実践論です。
当初これは、構造構成的医療論、構造構成的実践論などの原理論として構築していきました。
複数の原理論が開発できたため、それを踏まえて信念対立解明アプローチという領域を立ち上げました。
その成果は理論書としてまとめましたが、信念対立解明アプローチ研究は大学院時代の研究とはまったく別に取り組んでいます。
実は他にもいろいろな研究テーマで取り組みましたが。
こんな感じで、皆さんも複数の研究テーマに取り組むとよいですよ。
信念対立解明アプローチがどのような理論なのか以下の記事で詳しく紹介しています。
時流にのった売れそうな研究テーマの見つけ方
ただし、時流にのった売れそうな研究テーマを見抜くのはとても難しいです。
売れたかどうかは後になってみないとわからないですし。
1つの方法としては、JREC-INのチェックが上げられます。
ここを見ていると、現時点でどのような領域でどんな人材が求められているのか、が何となくつかめていきます。
ただ、この方法の弱点は、いま流行っている研究テーマがわかるだけで、次に何が来そうかはわからないところにあります。
まとめ
本記事では、「大学院生が生き残るにはどうしたらよいの?」という疑問に応えました。
実りある大学院生活をお過ごしください!
なお、以下より研究計画書の書き方について無料で学ぶことができます。ぜひ、ご参加ください。


Warning: Undefined array key 0 in /home/miracleusagi/kyougokumakoto.com/public_html/wp-content/themes/jinr/include/shortcode.php on line 306