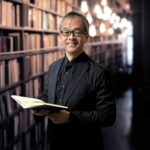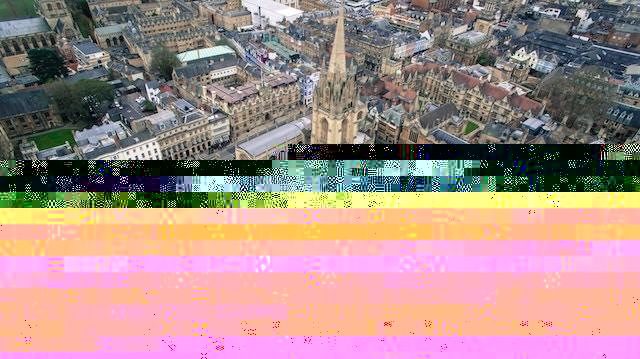【解説】CMOP、CMOP-E、CanMOPとは? カナダ作業療法モデル【入門】
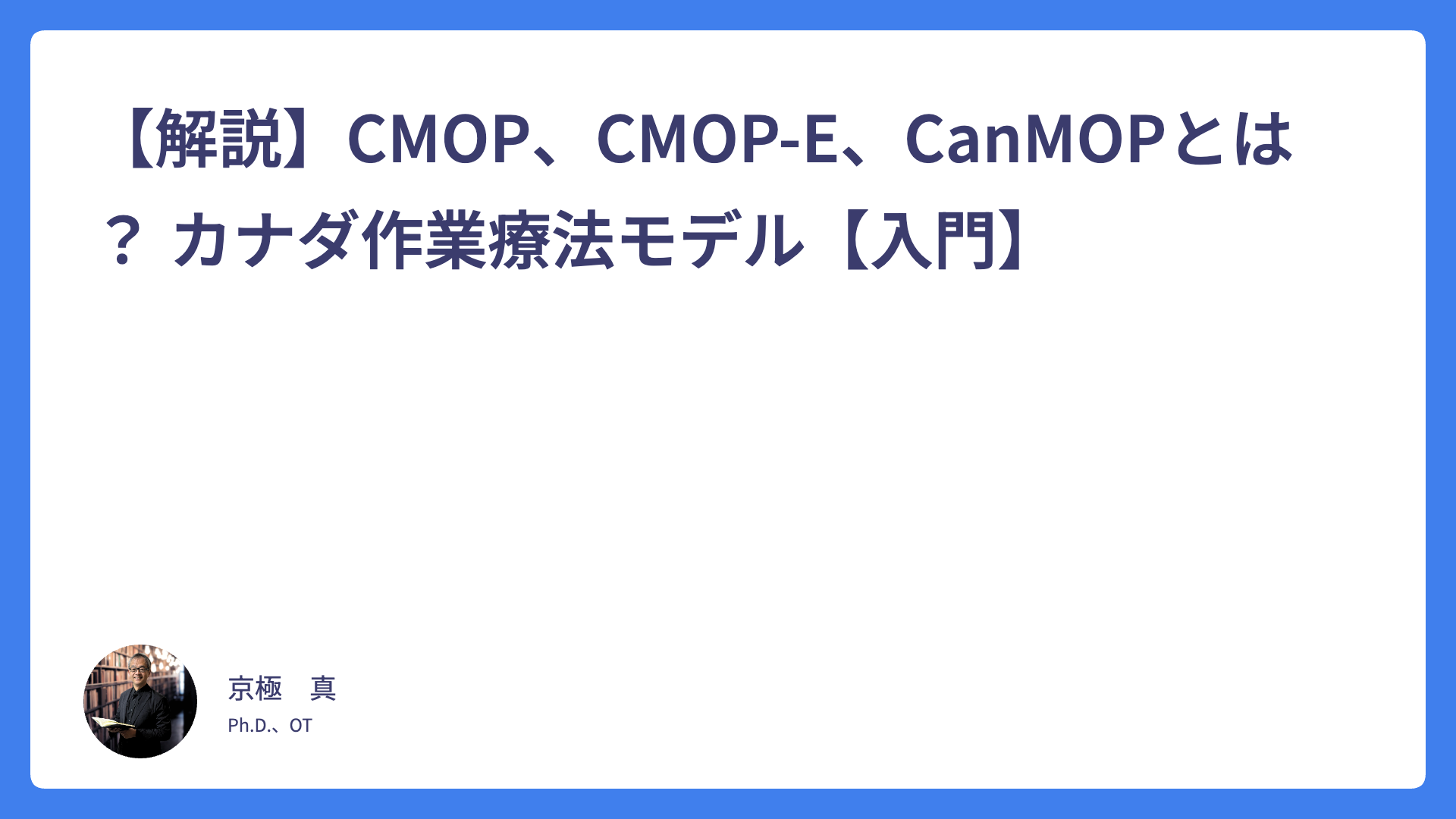
「作業療法士になったけど、理論モデルってたくさんあって難しい…」
「CMOPとかCMOP-Eとか、CanMOPって聞いたことはあるけど、違いがよくわからない…」
そんなお悩みを持つ作業療法士を対象に、この記事では、カナダで開発された作業療法モデルであるCMOP、CMOP-E、CanMOPについて解説します。
これらのモデルを理解することは、日々の臨床実践でクライエントの複雑な状況を捉え、より効果的な支援を提供するための助けとなります。
それでは早速、本題に入りましょう。
最新AIの音声による解説もどうぞ。
1. まずは基本から:作業療法と理論モデルの役割
作業療法士は、クライエントがその人らしい「作業」を行えるように支援する専門職です。ここでいう「作業」とは、日常生活で行うすべての活動(食事、入浴、仕事、趣味など)を指します。
- 作業療法の基本:作業療法士は、作業療法プロセスを通して、「作業」を起点に考え(occupation-centered)、「作業」に焦点を当て(occupation-focused)、「作業」を活かす方法(occupation-based)を実行します。
- 理論モデルの役割:クライエントが抱える問題は複雑です。理論モデルは、その複雑な状況を整理し、理解し、効果的な支援を計画・実行するための地図のような役割を果たします。
2. CMOP:作業「遂行」に着目したモデル
CMOP (Canadian Model of Occupational Performance) は、1997年に登場したモデルです(原型は1980年代)。
- 核となる焦点:作業遂行 (Occupational Performance) 。
- 作業遂行とは、クライエントが自分にとって意味のある作業を「選択」し、「計画」し、満足のいくように「実行」する能力のことです。
- 考え方:作業遂行は、「人」「環境」「作業」の3つの要素が相互に作用し合った結果として現れると考えます。
- ポイント:CMOPは、クライエントが特定の作業を「できるかどうか」「どのように行うか」という、作業遂行そのものに焦点を当てています。
Canadian Association of Occupational Therapists, Townsend E. Enabling occupation: an occupational therapy perspective. Ottawa: Canadian Association of Occupational Therapists; 1997.
3. CMOP-E:「作業との結びつき」という視点を追加
CMOP-E (Canadian Model of Occupational Performance and Engagement) は、2007年に登場し、CMOPを拡張したモデルです。
- 核となる焦点:作業遂行 (Occupational Performance) + 作業との結びつき (Occupational Engagement)。
- 作業遂行はCMOPと同様の考え方です。
- 作業との結びつきとは、単に作業ができるかだけでなく、その作業に「どのように関わっているか」「どれくらい没頭しているか」「どの程度、能動的に取り組んでいるか」といった、作業と人との関係性の質や深さ、主観的な体験を重視する概念です。
- ポイント:CMOP-Eは、「できるか」に加えて、「どのように作業に関与しているか」という質的な側面にも目を向けます。例えば、料理はできる(遂行)けれど、義務的にやっていて楽しめていない(結びつきが弱い)といった状況を捉えることができます。
Townsend EA, Polatajko HJ, ed. Enabling occupation II: advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE; 2007.
4. CanMOP:より広い視点「作業参加」へ
CanMOP (Canadian Model of Occupational Participation) は、2022年に登場した最も新しいモデルです。
- 核となる焦点:作業参加 (Occupational Participation) 。
- 作業参加とは、クライエントが自分にとって意味のある人間関係や文脈の中で、価値ある作業への「アクセス」を持ち、それを「開始」し、「持続」することです。
- 考え方:「遂行(できるか)」や「結びつき(どう関わるか)」を包含しつつ、さらに広い視点を提供します。
- ポイント:CanMOPでは、「その人にとって価値ある作業を、望む方法で、望む場所で、望む人々と、アクセスし、始め、そして続けられるか」という、実生活における持続可能な参加を最も重視します。作業遂行や結びつきも考慮しますが、それらが最終的に「参加」にどう繋がるかを見据えます。例えば、買い物に行ける能力(遂行)があっても、道が悪くてアクセスできない、転倒が怖くて始められない、疲れて続けられないといった障壁があれば、「参加」は妨げられます。
Egan M, Restall G ed. Promoting occupational participation: Collaborative relationship-focused occupational therapy. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE; 2022.
5. 3つのモデルの共通点と相違点まとめ
- 共通点
- すべてカナダで開発された作業療法モデル。
- 「作業」が人間の健康と幸福の中心であると考えている。
- 「人間」「環境」「作業」の相互作用を重視している。
- 相違点(進化のポイント)
- 焦点の進化:作業遂行 (CMOP) → 作業遂行+作業との結びつき (CMOP-E) → 作業参加 (CanMOP) へと、より広く、文脈や意味、持続可能性を重視する視点へと発展してきた。
- 作業の捉え方:単なる実行能力から、関与の質、そして実生活でのアクセスや持続可能性へと、捉え方が深まっている。
6. まとめ:CanMOPを理解して、より良い支援へ
CMOP、CMOP-E、CanMOPは、カナダで開発され、進化してきた作業療法モデルです。
- CMOP:作業を「できるか」 (作業遂行) に焦点。
- CMOP-E:「できるか」に加え、「どう関わるか」 (作業との結びつき) も重視。
- CanMOP:「できるか」「どう関わるか」を踏まえつつ、最終的に「その人らしい参加 (作業参加)」を持続できるかに焦点。
特に最新のCanMOPは、クライエントが直面する複雑な状況(個人の能力だけでなく、環境や社会的な要因も含めて)を深く理解し、その人らしい「作業参加」を支援するための強力なツールとなります。
これらのモデルの理解を深め、日々の実践に活かしていくことで、よりクライエント中心の効果的な作業療法を提供できるようになるでしょう。