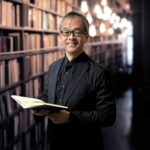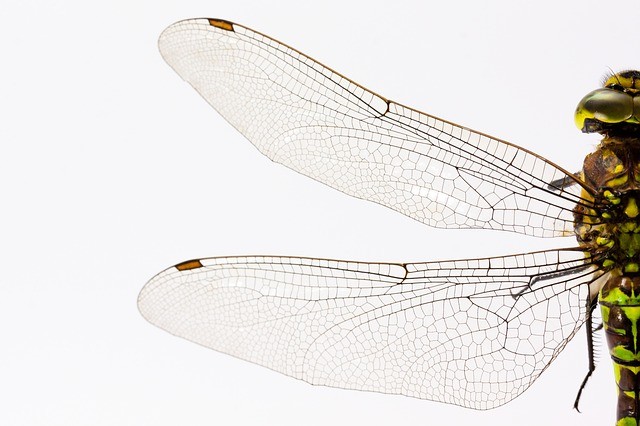【事実】モチベーションがゼロでも研究し続けるコツ【研究者が語る】
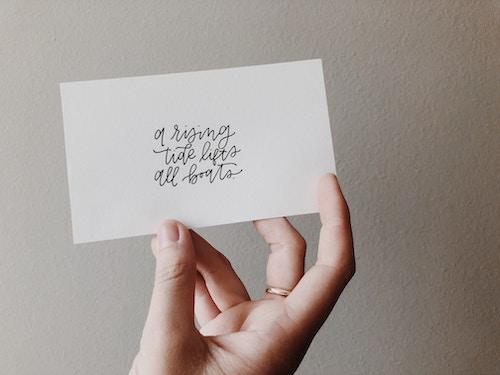
本記事では「研究のモチベーションがだだ下がりです。モチベーションがなくなったら研究オワコンですか」という疑問にお答えします。
- 研究の継続にモチベーションは必要ない件
- モチベーションがゼロでも研究し続けるコツ
本題に入る前にお知らせです。私が代表を務めるThriver Projectでは、無料Webセミナーを開催しています。研究論文や研究計画書の書き方のコツを、わかりやすく丁寧に解説しています。この無料Webセミナーでは約300名以上の方が学んでおり、参加者からはたいへん好評を博しています。これらの書き方で悩んでいる方は、以下のリンクからアクセスしてください。皆さんの参加を心からお待ちしています。
【無料】IMRaDを使った研究論文の書き方講座【Webセミナー】 (thriver.one)
【無料】研究計画書の書き方講座【Webセミナー】 (thriver.one)
研究の継続にモチベーションは必要ない件
事実として、研究の継続にモチベーションは必要ないです。
ぼくらの日常をふり返るとわかるように、モチベーションがゼロでもやり続けていることってわりとありますよね。
その最たる例が、仕事です。
資本主義において、労働者にとって仕事は搾取される機会に過ぎません。
例えば、ぼくら労働者が20万円の収入をもらうには、その3倍の60万円ほど稼がないといけません。
残り40万円は資本家にピンハネされているわけです。
そうやって搾取され続けていると、最初は仕事のモチベーションが高くてもだんだんなくなってくるものです。
だからといって、「仕事の継続しない。もう辞める」とはリニアーにつながらないですよね。
皆さん「仕事のやる気ゼロ…」と感じつつも、過度に手抜きすることなく、それなりに成果を出しているわけです。
研究の継続もそれと構造上同じです。
ある条件を満たすことができれば、モチベーションがゼロでも研究は継続できるんです。
なお、搾取の話を詳しく知りたい人は以下の記事でおすすめ本をまとめているので、ぜひお読みください。
モチベーションがゼロでも研究し続けるコツ
さて、ではモチベーションがゼロでも研究し続けるための条件とは何でしょうか。
結論から言うと、その条件は以下の3つです。
- その①:役割
- その②:習慣
- その③:環境
この3つの条件を満たすことができれば、モチベーションがゼロでも研究し続けることができます。
なお、役割、習慣、環境の重要性は人間作業モデルという理論から導出できるアプローチです。
その①:役割
役割はぼくたちに義務感を与えるものです。
例えば、労働者という役割は、決まった時間に決まった場所にいって、決まった課題に取り組むという行動を果たすように求めてきます。
同様に、研究者という役割は、決まった時間に決まった場所で決まった研究テーマに取り組むべし、という力動を放ちます。
役割は、本人の自覚と周囲の期待の相互作用によって構築されます。
つまり、自分自身が研究者だという認識をもち、周囲からの「ちゃんと研究しろ」という期待値を受け取ることによって、だんだん義務化していきます。
つまり、役割を構築するには自他に「強いられる」状態を作ることが肝要です。
なので、研究を義務化するには、ルールを設けて強いることがわりと重要です。
- 早朝から論文を書く→論文を書かないと他の業務に取り組まない
- 共同で研究を遂行する→自分が遂行しないと他の人に迷惑をかける
- 平日に論文を書く→書けないときは土日返上で論文を書く
こんな感じでルールを設けておくと、研究のモチベーションがゼロでも義務化するので研究し続けることができます。
その②:習慣
次に、研究習慣を構築する必要があります。
習慣とは、半自動的に行動できる状態を意味しています。
習慣は本人のモチベーションに関係なくやっちゃう行動です。
なので、研究の習慣化ができれば、モチベーションがゼロでも研究し続けることができます。
わかりやすい例でいうと、仕事のモチベーションがゼロでも、勤務があるときは深く考えることなく出勤の準備をし、出社したら課題をこなして働きますよね。
これは、仕事が習慣化しているから、やる気なくても半自動的にやっちゃっている状態を表しています。
研究も同様に、モチベーションがゼロでも習慣化することができれば半自動的に継続できるものなのです。
研究を役割として遂行する状態を3ヶ月ほど続けると、研究習慣が構築されていきます。
最初は役割のプレッシャーでやり続けているのでしんどいです。
けど、3ヶ月ほど経過したら、むしろ研究しないとやることなくてしんどいです。
モチベーションがゼロでも研究習慣が身につければ研究し続けることができるので、最初はしんどくてもふんばるべしです。
- 研究を役割化する
- 3ヶ月ほど頑張る
- 研究習慣が作られる
その③:環境
「役割→習慣」で行動変容しつつ、環境調整することも重要です。
特に「一緒に頑張る仲間を作る」という人的環境の調整が有効かなと思います。
例えば、ぼくは大学院生時代に他領域で圧倒的な努力を重ねる仲間達に囲まれていました。
例えば、家に帰ることなく研究室で寝泊まりしながら研究し続ける人、飲み会があったとしてもその後に朝まで1人で研究し続ける人、毎月のように原著論文を投稿し続ける人、などといった猛者たちとともに研鑽を積んだんです。
突き抜けた人たちとの関係を構築し、ともに研鑽を積むにようになるとモチベーションがゼロでも研究しなければならないと思いさだめることができます。
周囲にそういう仲間がいない人で、これから研究を本格的にやりたい人は大学院に進むのもおすすめです(^^)/。
機能している大学院は、圧倒的に頑張っている人がいるものなので、よい刺激を受けつつモチベーションがゼロでも研究を継続できるようになりやすいです。
まとめ:モチベーションがゼロでも研究し続けるコツ
本記事では「研究のモチベーションがだだ下がりです。モチベーションがなくなったら研究オワコンですか」という疑問にお答えしました。
結論をいえば、ある条件を満たせばモチベーションがゼロでも研究を継続できます。
なお、それらの条件を満たしても、研究し続けることが苦痛な人は他の道に進むべしです。
人生は短いので、苦痛なことを続ける暇はありませんよ。
なので、そういう人は思いきって新しいことに挑戦してみましょう。