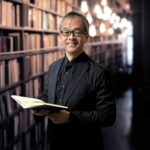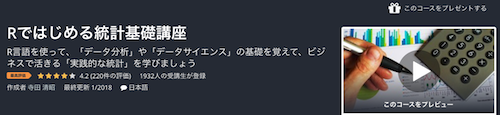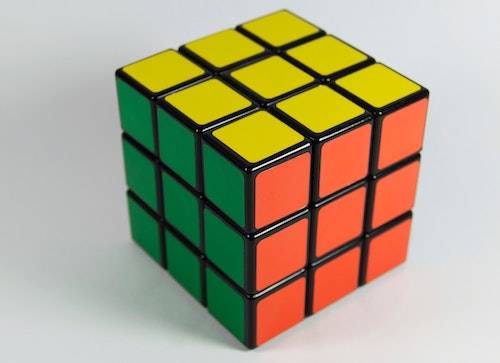事例研究のポイント


本記事では「事例研究をするときのポイントはどんなところですか」という疑問にお答えします
事例研究のポイント
個別の事例から一般化できそうな仮説(法則)を抽出すること
事例研究のポイントは、上記の通り非常に高度でアクロバティックな知的営為に求められるます。(いろんな解釈がありますけど)
そのため、真面目にやると大変です。
事例研究は「研究」である以上、大なり小なり一般化可能性をめがけることになりますが、単一の事例から全体に通じうる法則を見いだすのは至難の業なんです。
院内事例検討と、学術的事例研究では求められるものが違う
院内の事例検討(事例報告)の場合
実践の経過を報告し、その意味を内省し、よりよい実践になるような知見を得るもので十分です。
事例検討は日々の臨床の改善のために行いますから、それに役立つなら個別の事例から全体に通底しうる法則の生成までやらなくてもよいです。
これだってけっこう難しいことなんですけどね。
学術的事例研究の場合
個別の事例の作業療法プロセスを分析し、そこからいろんな事例に共通しそうな仮説を生成し、次の新しい事例研究、質的研究、量的研究へつなげられる努力が求められる。
当然、事例研究の報告にあたっては先行研究のレビューが必要ですし、考察でも先行研究を踏まえて何が新しい知見なのかを明確に示す必要もあります。
そのため、何が新しいかわからない事例研究は、けっこうキツいといえます。
事例研究は仮説の生成と検証のプロセスであり、事例研究の質はそこで判断することができるんですよ。
良質な事例研究は臨床を改良しますし、学知の発展にも貢献できます。
めっちゃ難しいですけど。
事例研究について理解を深めたい人におすすめの本は、以下の2つの記事がオススメです。
まとめ:事例研究のポイント
本記事では「事例研究をするときのポイントはどんなところですか」という疑問にお答えしました。
事例研究とは言っても、院内で行う事例検討と学術的な事例研究とでは求められるものが違います。
何が新しいのかわかないような事例研究ではなく、個別の事例から一般化できそうな仮説を抽出することが求められます。
そのため、とても大変で骨の折れるようなものになります。
ですが、とてもやりがいのある研究になるでしょう。
Warning: Undefined array key 0 in /home/miracleusagi/kyougokumakoto.com/public_html/wp-content/themes/jinr/include/shortcode.php on line 306