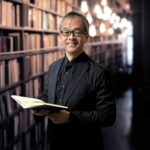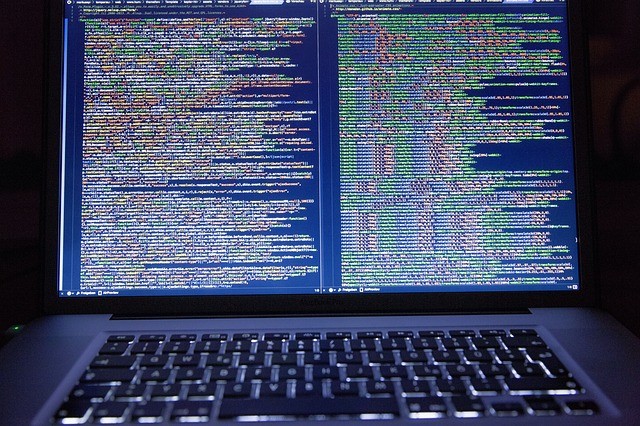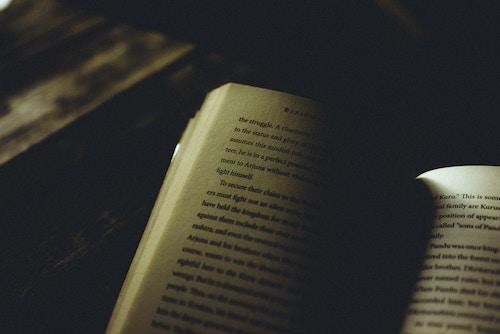【これ読むべし】事例報告の方法を学べる本【3冊+1】

本記事では「事例報告の方法を学べる本が知りたいです。何かおすすめ本はありますか?」という疑問にお答えします
- 事例報告の機能
- 事例報告の方法を学べる本3冊【もちろん厳選しています】
- 国際基準にそった事例報告の書き方を学びたいなら〇〇がオススメ!
- 事例報告したいなら今すぐやるべきこと
事例報告の機能
事例報告には他の研究法にはない機能があります。
具体的に言いますと、事例報告は以下のような事柄に関する仮説を生成できます。
- 未知のあるいは希な事象
- 新しい疾患・障害に対する評価・治療
- 評価・治療に対する有害な反応
- 新しい理論・評価・治療の臨床応用
- 予想外の臨床経過 など
事例報告の機能は新規性のある事象に適用しやすく、例えば世界初の心臓移植手術は事例報告によって発表されています。
また事例報告の機能は日々の臨床実践を通して知識と技術を構造化しやすいものであるため、特に臨床家にあった方法であるといえます。
事例報告の方法を学べる本3冊【もちろん厳選しています】
EBM時代の症例報告
中古品しかないのがとても残念ですけども、これは必読書。
ヘルスケア領域で事例報告が重要な理由、その方法について詳しく論じています。
事例報告はときに随筆っぽくなってしまい、そこから新たな仮説を生成できていないものが散見されますが、本書はそうした事態を回避しながら事例報告をエビデンスとして示すコツを実例付で示しています。
医学書院さんにはぜひ再版してほしい一冊です。
事例研究というパラダイム〜臨床心理学と医学をむすぶ
こちらも名著。
事例報告に対する批判として「非科学的」というものがありまして、本書は事例報告の科学論から問い直すことによってそれを基礎づけ、実践科学研究として事例報告を位置づけます。
また事例報告の例も豊富であり、そのあり方や意義を理解しやすいです。
副題で臨床心理学と医学を銘打っていますが、それ以外の領域のひとも手元においておきたい一冊です。
論文作成ABC〜うまいケースレポート作成のコツ
上記2冊が事例報告の哲学的な側面から詳解しているのに対して、本書は具体的なHow toを論じているので速効で役立ちます。
特にQ&Aは秀逸でして、以下にその一部を示しますが、 初心者が事例報告で体験する疑問と回答がわかりやすく示されています。
- rejectされてしまいました。IFの低い雑誌へ横滑りさせていいでしょうか?
- 投稿サイトまで進んだら、「文献引用はバンクバー方式にしてある」にチェックを入れる欄があります。バンクバー方式とは何ですか?
- 投稿すべき雑誌は教授、准教授、部長にうかがえばいいのですね? などなど
具体的なノウハウを知りたい人はぜひどうぞです。
国際基準にそった事例報告の書き方を学びたいなら〇〇がオススメ!
上記3冊の書籍は自信をもってオススメできる事例報告本ですが、実はぼくもnoteで【初心者向け】国際基準にそった事例報告の書き方【研究者が指南する】というweb教科書を公表しております。
これの大きな特徴は、CAREガイドライン(CAse REport guideline)という事例報告の国際基準にそった書き方のコツを指南しているところにあります。
- タイトル
- キーワード
- 要旨
- はじめに
- 患者情報
- 臨床所見
- 経過
- 診断・評価
- 治療・介入
- フォローアップとアウトカム
- 考察
- 患者の視点
- インフォームドコンセント
【初心者向け】国際基準にそった事例報告の書き方【研究者が指南する】はQ&Aも充実しており、購入者向けの相談コーナーもあります。
上記3冊の書籍とあわせてご活用していただければと思います。
事例報告したいなら今すぐやるべきこと
他の研究法と同様に、本を読んだだけで事例報告ができるようになるわけではありません。
重要なことは以下の1〜4のサイクルをしっかり回すことです。
- 本などで知識を学ぶ
- 臨床する
- 事例報告を発表する
- 1〜3のstepを自己評価する
事例報告ができるようになるためには実際に行うことが重要でして、本記事で厳選紹介した文献を読みながら実際に実行してみることが不可欠です。
途中でつまづいたらメンターに相談したり、【初心者向け】国際基準にそった事例報告の書き方【研究者が指南する】の購入者向け相談コーナーを活用してください。
まとめ
本記事では「事例報告の方法を学べる本が知りたいです。何かおすすめ本はありますか?」という疑問にお答えしました。
本記事が事例報告に関心がある人の役に立てばうれしいです。
本記事では、事例報告におすすめの本を紹介しましたが、他の研究についても参考にすると良い本があります。
以下の記事で研究を学べる本をまとめました。
どんな本を読めばいいのかお探しの方は以下からどうぞ!!