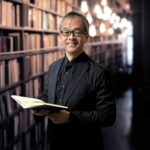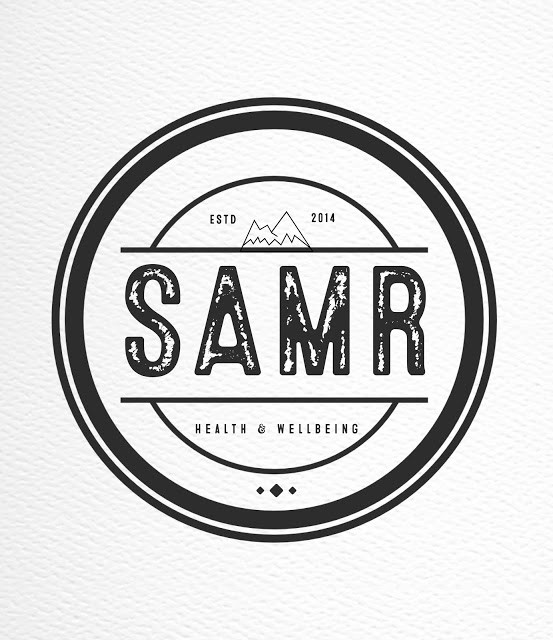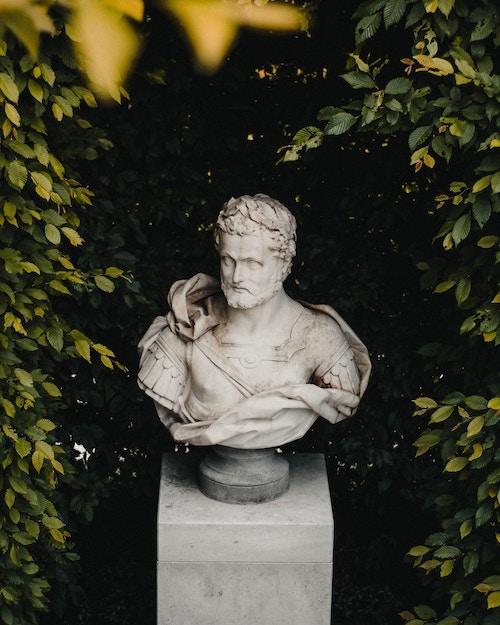Mplusのお薦め資料やサイト
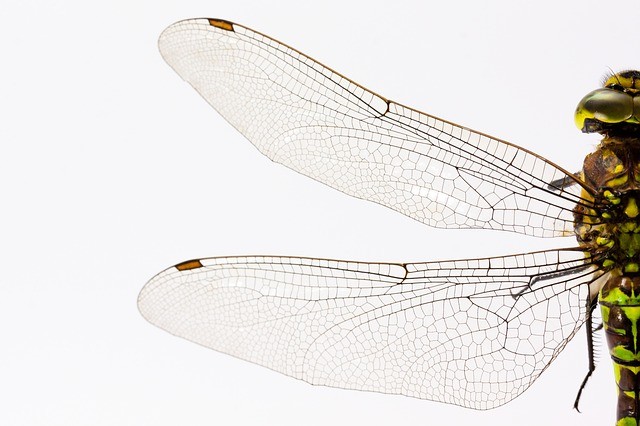

本記事では「Mplusのお薦め資料やサイト」についてサクッと紹介します
Mplusのお薦め資料やサイト
Mplusとは
Mplusは構造方程式モデリングのための統計ソフトで、Amosでできることは全部できるだけでなく、AMOSではできない複雑な分析も実行できる優れたツールです。
例えば、構造方程式モデリングの枠組みで探索的因子分析やカテゴリカル因子分析を実行したり、マルチレベル分析と構造方程式モデリングを組み合わせたり、いろいろできます。
その柔軟さといったら、本当にすごい。
ソフトは基本構成のMplus Base Program、Add-on付のMplus Base Program and Mixture Add-On、Mplus Base Program and Multilevel Add-On、Mplus Base Program and Combination Add-Onがあります。
Mplusの全機能を使うにはMplus Base Program and Combination Add-Onが必要です。
これはもう迷うことなくMplus Base Program and Combination Add-Onを買うべし。
購入は下記のサイトから
なおMplus Base Programを買ってしまい、後からAdd-Onを追加したいときは、開発者に連絡すると個別に対応してくれます。
対応は迅速で丁寧なので助かります。
でも、MlpusはCUIを採用しており、日本語対応していないので、最初のハードルはAmosよりもかなり高いです。
ぼく自身と言えば、さいしょは時間がないなかで、よくわからないエラーが連発し、ちょっと泪目になりそうでした。
そんなとき非常に役だったのは、下記の本とサイトです。
まとめておくので、Mplusを使いはじめたけどよくわからない、という人はぜひご参照くださいませ。下記の本は手元に持っておいて損なし。
著者の清水さんのサイト。
上記の本にも載っていない解説があって役立ちます。
僕の質問にも丁寧に対応してくださって非常に助かりました。
感謝!
清水さんが開発しているHADも秀逸で僕も使ってます。
Mplusの公式Manual
英語だけど、わかりやすい。
必読。
Mplusの公式掲示板
最初はエラーではじかることが多いので、掲示板で対応を確認すると解決できることがあった。
わからないときは開発者にメールで問い合わせ。
以下のスライドは印刷して、本と一緒に携帯するとよい
Warning: Undefined array key 0 in /home/miracleusagi/kyougokumakoto.com/public_html/wp-content/themes/jinr/include/shortcode.php on line 306