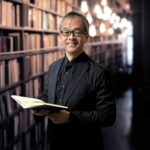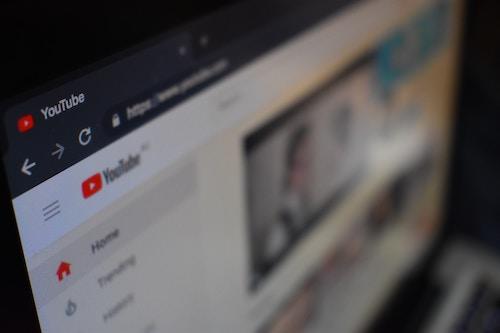【初心者向け】情報発信おすすめツール【厳選3つ】

本記事では「インターネットが発展して、気軽に情報発信できるようになったと思うのですが、ツールがいろいろありすぎてどれを使ったらよいかわかりません。これからインターネットで情報発信するにあたって、おすすめのツールはありますか」という疑問にお答えします
- インターネットで積極的に情報発信していきたい
- おすすめの情報発信ツールを知りたい
本記事を書いているぼくは作業療法士ですが、研究論文や著書などの執筆に加えて、わりとインターネット上でも積極的に情報発信しています。
特に以下のツールをよく使っています。
- blog
- X(旧:Twitter)
- YouTube
- note
特に、ぼくのような専門家は研究論文や著書の発表が一番重要であるものの、それのみに頼った情報発信は非効率です。
また学会発表は人とのつながりを作る点で優秀ですけど、情報発信という点でいうとやっぱ非効率です。
なので、上記のような情報発信ツールを使いこなせる技術はわりと必須かと思います。
本記事ではそんなぼくが、これから情報発信する人向けにおすすめのツールを厳選紹介します。
情報発信おすすめツールを選ぶ基準
情報発信おすすめツールを選ぶ基準は2つあります。
- 流動性がある
- 拡散性がある
基準1:流動性がある
インターネットって世界に開かれていますが、ツールの選び方を間違えると情報発信しても誰も見てくれない、という事態に陥ります。
実際にインターネットで情報発信するとわかりますが、案外多くの人に見てもらえないんですよね。
なので、ある程度多くの人が往来しているツールを活用することはめちゃ重要です。
せっかくインターネットで情報発信するんですから、過疎っているツールを使わないようにしましょう。
基準2:拡散性がある
次に、情報が拡散しやすいツールを選択した方がいいです。
情報の拡散性というとSNSのバズを思い浮かべるかもしれませんが、これにはSEOによる検索流入も含まれます。
SNSでバズらせるのが得意な方はあまり気にしなくてもよいですが、これから情報発信するならば2つの情報の拡散性に開かれたツールを使った方がいいです。
その方が多くの人に見てもらいやすいので、情報発信する目的を達成しやすいです。
情報発信おすすめツール【厳選3つ】
以上を踏まえたうえで、ぼくがおすすめする情報発信ツールは以下の3つです。
- blog
- X(旧:Twitter)
- YouTube
ぼくは他にもInstagram、note、Facebookなども使っていますが、これから情報発信するならば上記の3ツールの使用をおすすめしたいです。
理由は流動性と拡散性の両方を高水準で満たしているからです。
もちろん、Instagram、note、Facebookもよいですし、ぼくも実際によく活用しています。
けど、人目に触れやすいかというと、Blog、YouTube、X(旧:Twitter)に比べると、ちょっと微妙な感じがしています。
本気で情報発信したい人は、ぼくみたいに全部使えばよいですけど、これから情報発信ツールを活用したいならまずはBlog、YouTube、X(旧:Twitter)から攻略するとよいかと思います。
Blog
Blogは昔からあるメディアですが、これは今でも十分強力な情報発信ツールです。
まとまった情報を発信するにはBlog以上のツールはないです。
BlogはSEO対策をきっちりやれば検索流入を確保できますし、後述するTwitterと連携させればSNSで拡散することも簡単にできます。
また、Blogは他の情報発信ツールをまとめる母艦としても機能するので、あなたの情報発信に対して興味をもってくれた人に見取り図を提供できます。
Blogは有料と無料がありますが、ぼくの個人的経験でいえば有料のWordpressが圧倒的にオススメです。
ぼくの感触では有料Blogの方がSEOが強いので、情報発信の効率が格段によいです。
YouTube
これからの時代を考えると、YouTubeもおすすめ情報発信ツールです。
YouTubeは多くの人が利用しますし、SEOにもSNSにも対応しており、上述のおすすめ情報発信ツールの選定基準を満たします。
ただ、やってみればわかりますが、YouTubeって外部流入がほとんどありません。
YouTubeはYouTube内で人が動いていますので、実際にはなかなか見てもらえないです。
けど、もうすぐ5G時代がやってくると考えると、ぼくも毎日YouTubeに動画をアップしているぐらい可能性を感じる情報発信ツールです。
いまライブ配信はInstagramでやっていますが、これもそのうちYouTubeに切りかえる予定です。
顔出しが嫌な人はVtuberという手段もあるので、積極的に検討するとよいです。
X(旧:Twitter)
X(旧:Twitter)もおすすめ情報発信ツールです。
X(旧:Twitter)は検索流入もありますが、それよりも情報の拡散性に特に優れています。
なので、X(旧:Twitter)はBlogやYouTubeで発信したまとまった情報を広報するために使うとよいです。
また、特定のトピックをX(旧:Twitter)でつぶやき、反応がよかった内容をBlogやYouTubeで深掘りするという手段もわりとおすすめです。
Twitterは情報の断片が点在するので、自身の専門性に関する内容を情報発信したいと思ったら、BlogとYouTubeとの併用しなきゃ何を発信しているかわかりにくくなります。
X(旧:Twitter)はBlogやYouTubeと併用することで、より効率的に情報発信しやすくなります。
情報発信おすすめツールを活用したい人におすすめ本
これから情報発信おすすめツールを活用したい人は以下の本を読んでおくとよいです。
- 沈黙のWebマーケティング −Webマーケッター ボーンの逆襲
- 動画2.0 VISUAL STORYTELLING
- SNSで夢を叶える ニートだった私の人生を変えた発信力の育て方
沈黙のWebマーケティング −Webマーケッター ボーンの逆襲
SEO対策の基本を学べる良書です。
BlogはSEO対策しないと検索流入がマジで伸びないです。
ぼくはBlog歴は数年ありますが、SEO対策したのは2018年7月からでして、もっと前からSEO対策しておけばよかったと後悔しています、笑。
なので、情報発信ツールとしてBlogを活用したい人は、本書でSEO対策を学ぶとよいです。
動画2.0 VISUAL STORYTELLING
情報発信ツールとしてYouTubeを活用したい人は必読。
現状、YouTubeはエンタメ系が中心です。
けど本書を読めば、これから5G時代がやってくることあって、専門系、教育系、ビジネス系の動画が伸びると理解できると思います。
SNSで夢を叶える ニートだった私の人生を変えた発信力の育て方
SNSの攻略は失敗と試行錯誤の連続であるとわかって、勇気がもらえる本です。
インターネットって簡単に情報発信できますが、情報を届けたい人たちに届けられるようになるには、めちゃくちゃ地道な取り組みが必要です。
BlogにしてもYouTubeにしても、スプーンで地面を掘るような感覚でして、ほとんどの人がたぶん途中で挫折します。
本書を読むと、試行錯誤しながら攻略していく利点がわかって、めちゃくちゃ大変だなぁと思ったときにふんばれます。
まとめ:情報発信おすすめツール
本記事では「インターネットが発展して、気軽に情報発信できるようになったと思うのですが、ツールがいろいろありすぎてどれを使ったらよいかわかりません。これからインターネットで情報発信するにあたって、おすすめのツールはありますか」という疑問にお答えしました。
結論を言うと、これからインターネットで情報発信したい人にオススメのツールは以下の通りです。
- blog
- X(旧:Twitter)
- YouTube
特に、ぼくのような専門家は従来の学会や学術誌にのみ頼っていると非効率なので、上記のような情報発信ツールを使いこなせるとよいですよ。
なお、ぼくは主に以下のツールを活用しているので、よろしければアクセスしてみてください。
- blog
- X(旧:Twitter)
- YouTube
- note