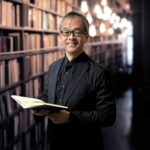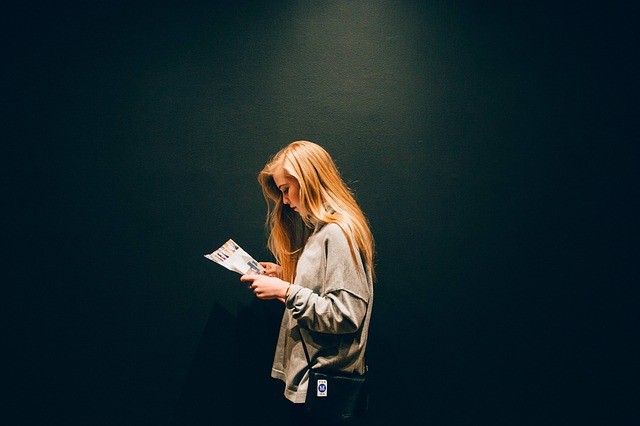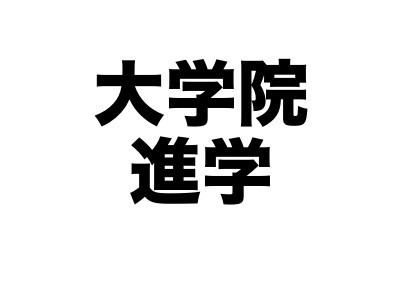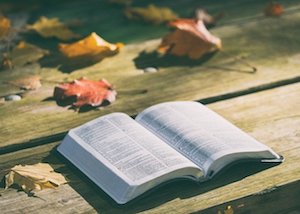【初心者向け】研究テーマが決まらない人の特徴は悩みすぎです

本記事では「研究が手詰まり状態です。現在、大学院生なんですが、研究テーマが決まらないです。いろいろ考えているうちに、どうしていいかわからなくなります。どうしたらいいですか」という疑問にお答えします。
- 研究テーマが決まらないと悩んでいる
- 研究テーマを決められるようになりたい
ぼくは、研究テーマを決めることで困ることがありません。ですが、ぼくの周りでも研究テーマを決めることで悩む人は多いです。
ぼく:直感で決めるため、困ったことがない
院生:決められず、悩んでいることがある
そんなこともあり、研究テーマを決める支援をずっとやっています。
本題に入る前にお知らせです。私が代表を務めるThriver Projectでは、無料Webセミナーを開催しています。研究論文や研究計画書の書き方のコツを、わかりやすく丁寧に解説しています。この無料Webセミナーでは約300名以上の方が学んでおり、参加者からはたいへん好評を博しています。これらの書き方で悩んでいる方は、以下のリンクからアクセスしてください。皆さんの参加を心からお待ちしています。
【無料】IMRaDを使った研究論文の書き方講座【Webセミナー】 (thriver.one)
【無料】研究計画書の書き方講座【Webセミナー】 (thriver.one)
研究テーマが決まらない人の特徴は悩みすぎです

結論:研究テーマが決まらない人の特徴は悩みすぎです
研究テーマが決まらない人の特徴は、ズバリ悩みすぎなところです。
研究テーマが決まる人:
即断即決で「よし!じゃやってみよう!」と行動しはじめる
研究テーマが決まらない人:
うーん。でも作業って意味あるものばかりじゃないよな。
意味のない作業にも役割はあるはずだし、そうすると意味のある作業の役割を調べても、あまり意味がないんじゃないだろうか。
そもそも、最近の精神科作業療法は統合失調症のみの診断がついている人よりも、複数の診断がついた方が多いような気がする。
だとしたら、統合失調症をもつクライエントを対象にするのはどうなんだろうか。
あー、、、いろいろ考えていたらだんだんどうして良いかわからなくなってきたぞ。
そもそも私がこの研究をやらなくても、他の人がやってくれるんじゃなかろうか。
やばい。。。頭がこんがらがってきた。。。
こんな感じで、いろいろ悩んでしまうわけです。
よくある質問:研究テーマを決めるためにいろいろ考えることは大切では?
「研究テーマを決めるためにいろいろ考えることは大切では?」
もちろん、研究なので考えることは大切ですし、ぼくも研究テーマを決めるときは徹底的に考え抜きます。
考えることと悩むことはまったく違う
考えるとは、いくつかの論拠からある結論を導き出すこと
これはいくつかの論証形式にそって進むものですし、とことん考え抜くと何らかの結論がスパッと見えてくるものです。
研究テーマが決まる人:考える
研究テーマが決まらない人:悩む
悩むとは、いくつかの論拠からぐるぐる思考をめぐらして結論に達しない状態です。
なので、いくら悩んでも悩んでいるうちは研究テーマが決まることがない。
悩んでいると考えている気分になるが、実際には悩んでいるだけで考えていない。
研究テーマが決まらない人は、その点重々承知しておくべきです。
研究テーマが決まらない人が悩まずに考えられるようになる方法

本記事で解説する方法は以下の通り。
- その①:じくじくネガティブに悩み出したら先送りする
- その②:思考を整理するために身体を動かしてみる
- その③:スッキリした頭でしっかり考える
- その④:指導教員に相談する
その①:じくじくネガティブに悩み出したら先送りする
研究テーマが決まらない人は基本的に悩みすぎです。
なので、研究テーマを決めるときに、あれこれ悩みはじめたら、いったん中断して研究テーマの検討を先送りしてください。
じくじく悩んでいる間は、研究テーマを決めることはできないので、悩んでいるだけ時間の無駄
なので、あれこれ悩みはじめたら、その場は深追いせずにさくっと中断して先送りましょう。
その②:思考を整理するために身体を動かしてみる
次に、身体を思いっきり動かしてください。
座って考えているとじくじく悩みがちですが、ランニングしたり、筋トレしたりすると余計なことは考えられなくなります。
そのぶん、思考の整理が進むので研究テーマを決めやすくなります。
あれこれ悩みはじめたら、思考を整理するためにがっつり運動しましょう。
おすすめの運動は以下の記事でまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
その③:スッキリした頭でしっかり考える
運動することによって思考を整理できたら、研究テーマを決めるためにじっくり考え抜きましょう。
その際、思考のルールにそって考えることが重要です。
思考のルールは論証形式ともいいまして、悩むことなく考えるためにはわりと重要です。
なので、研究テーマが決められない人は思考のルールにそってしっかり考え抜き、よりよい研究テーマを決めましょう。
その④:指導教員・共同研究者に相談する
現在、大学院生の人は指導教員に相談したらよいです。
指導教員は大学院生が研究テーマを決めることも含めて支援するためにいるので、遠慮なくどんどん相談しましょう。
まともな指導教員でしたら、10分も話を聴けば研究テーマを設定に向けて支援できるはず
また、大学院に行っていないなら、共同研究者に相談するとよいでしょう。
共同研究者とともに悩まないようにしてください
以下の記事で詳しく紹介しています。
まとめ:研究テーマが決まらない人の特徴は悩みすぎです

本記事では「研究が手詰まり状態です。現在、大学院生なんですが、研究テーマが決まらないです。いろいろ考えているうちに、どうしていいかわからなくなります。どうしたらいいですか」という疑問にお答えしました。
結論を言えば、研究テーマが決まらない人の特徴は悩みすぎなところにあります。
この問題を解決するには以下の方法が考えられます。
- その①:じくじくネガティブに悩み出したら先送りする
- その②:思考を整理するために身体を動かしてみる
- その③:スッキリした頭でしっかり考える
- その④:指導教員に相談する
※大学院進学に関して記事を以下にまとめています。大学院進学を考えている人は参考にどうぞ!!